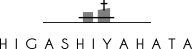2024/03/03
3/3巻頭言「『問い』に留まる―平和への道」
先日の若松英輔さんの講演で心に残ったことに「問いを大切にする」があった。「簡単に答えを与えてくれる人を私は信用しません」と若松さんは言う。
僕らは小中高と「正解がある」という前提で勉強してきた。テストでは「正解」はただ一つ存在した。それを的確に書くことが求められた。だが、一旦社会に出ると世界はそう単純ではなかった。何が「正解」かわからない。そんな現実をさまよい歩く。「解ったら生きられる」と考えていては生きていけない。「解らなくても生きる」。そんな生き方、そんな力が必要だった。「不可解性への耐性」だ。
にも拘わらず多くの人が「解り易さ」を求めている。そこに付け込み「不可解な現実」が無いかのように「明確」で「解りやすい」ことを言う人が現れる。最たるものが戦争指導者だ。世界を善と悪に二分し相手の存在を許さない。戦争は実にわかりやすい。しかし、そんな単純であるはずはない。どちらかが絶対に間違っていることも、どちらかが絶対に正しいこともない。あえて「絶対」というならば「戦争は絶対に間違っている」と言うべきであってどちらかが「正しい戦争」をしているということはない。だから「答えを与える人を信用しない」ということは大事な指摘だ。そして「問い」続けることが平和の道となる。
イエスは十字架上で「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マルコ15章34節)と叫んだ。最期のことば、それは「どうして」だった。イエスは「問い」の中に留まった。それが「平和の君」の姿だった。問われた神も「答え」を出さない。ただ沈黙のみ。
大切なのはイエスが「神に問うたこと」だと思う。「正解」は自分の中にはない。人の中にはないのだ。イエスは神の中に「正解」があると思っている。「答えをくれないなら神もいない」とは考えない。「正解」は神の中にあると信じていたのだ。「神の前で神無しに生きる」。これはナチスに抵抗したボンフェッファーの言葉だが、「正解の前で正解無しに生きる」とも読める。
直前、イエスはゲッセマネで「どうか、この杯をわたしから取りのけてください」(マルコ14章36節)と祈る。しかし最後には「しかし、わたしの思いではなく、みこころのままに」と祈りを閉じる。聖書では二つの祈りは連続している。が、私は先の祈りと後の祈りの間には弟子たちが眠りこけるほどの時間があったと思う。一時間、いや二時間。そしてついにイエスは自分にとって唯一の「正解」であった「杯を取りのける」を留保する。「正解」を脇に置き「みこころ」にゆだねる。「みこころ」、神の思いは人にとって「不可解」そのものである。「みこころ」に留まる。それは人間にとっては「不可解」に留まることだった。ここでもイエスは「問い」に留まったのだ。
私たちは「正解」を神に委ね「問い」に留まる。それが戦争の時代を生きる人間の倫理だ。支配者たちが提示する解りやすい「正解」にうかうかと乗ってはいけない。「なぜですか」と問い続ける人として私たちは出会いつながる。それが平和への道となると思う。