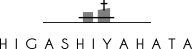2021/09/19
9/19巻頭言「あれから三年―松ちゃん、会いたいよ その㉒ 」
二人でお茶を飲む。いや、本当にいいお茶だった。松ちゃんは終始笑顔で僕の入れたお茶を飲んでいた。今後もこのままいくとは思えない。だが、この一歩は大きい。
その後、松ちゃんは2ヶ月ほどわが家で過ごし、近所に家を見つけた。大家さんの大きな屋敷の傍らに数軒の貸家があり、その内の一軒をお借りすることになった。この大家さんは90歳を超えておられたが、いつも長靴を履いてカブ(50ccのバイク)にまたがり時速5キロほどのスピードで町中を歩くように移動されていた。大工さんだったそうで、自身で借家の普請をされていた。私が保証人となり無事契約でき、松ちゃんは入居した。
そして3月。松ちゃんだけの「出発式」が行われることになった。「出発式」とは、自立支援住宅の半年を終えた方々が地域の生活に移行する時に行われる式である。これまで伴走してきた担当者から「励ましのことば」という卒業証書のようなものをもらう日である。出発する人は半年間の思いを語る。ある人は思いを文章にし、それが苦手な人は「ありがとう」とひとこと語る。先に出発した先輩たち、ボランティアなど毎回五十名程度が駆けつけ出発を祝う。
その場には、次の入居予定者も参加することになっている。この時点では野宿状態での参加となるが、数日後、彼らは自立支援住宅に入居する。彼らは、目の前で出発する人々に半年後の自分の姿を見る。何よりも重ねられたボランティア(担当者)との関係を見ることで、何が一番大切かを知る。
自立支援住宅は「自立を支援する」ために作られた。野宿状態というのは、最貧困状態である。家も仕事も何もかもを失っている。半年間でこれらを手に入れる。担当者やスタッフの第一の役割はこの「自立支援」である。しかし、それだけでは足りない。自立支援は、「宿無し」に象徴される「経済的困窮」に対する対処を意味する。私たちは、この「経済的困窮」を「ハウスレス」と呼んできた。これが解消されないと憲法で保障されている生存権、つまり「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことは叶わない。
一方で路上で「畳の上で死にたい」と語っていた人が、アパートに入居後に「俺の最期は誰が看取ってくれるだろうか」と仰る姿を何度も見てきた。「畳=住居」が無いことは、憲法に反する事態であるが、それが保障されれば十分かと言えばそうではない。足らないものがある。それが、あの「誰が」ということばに込められた思いなのだ。自立が孤立に終わっては意味がない。現に最初の頃、自立を果たした方が、その後「孤立死」状態で見つかることさえ起こった。私たちは、この「誰が」がいない状態、つまり家族や友人、心配してくれる人、自分を必要としてくれる人がいない状態を「ホームレス」と呼んだ。ハウスとホームは違うのだ。
つづく