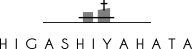2020/06/21
6/21巻頭言「ポストコロナを生きるために その➆」
飲食店もスポーツジムも休業自粛に追い込まれた。ライブハウスはスケープゴート状態でやり玉にあげられ、誰もいないステージからは声なき悲鳴が聞こえている。抱樸はと言えば、行動の8割自粛と言われてもそれは無理な相談で、一部の業務、例えば訪問活動(そもそも病院や施設へ立ち入が禁じられている)や就労訓練事業のレストランなどは休業に追い込まれたが、それ以外の活動は困窮者の増加に従い忙しくなっている。抱樸の活動のベースともいえる炊き出しは「一緒に過ごす」ということが出来なくなり、弁当や物資を配り終えた途端解散とならざるを得ない。くやしさを晴らすためボランティア部の呼びかけで全国の支援者も手紙を書いてくれ、弁当に添えている。「ねぐら」に戻りひっそりつながりを確かめる日々。
抱樸の支援は「伴走型支援」と呼ばれ「濃厚接触」が売りだった。「伴走型支援」とは、従来の課題解決型が目的の支援では無く、「つながり(伴走)」を目的とした支援である。それはひとえに、この社会の「孤立化」が深刻な事態となっていたからだ。これは、「新型コロナ」以前からあった、社会そのものの問題であった。
今から32年前。1988年12月NPO法人抱樸は、おにぎりと豚汁をもって野宿する人々をひとり、ひとりと訪ねることから活動を開始した。炊き出しだけでは問題の解決にはならない。1990年頃から居住支援が始まる。路上生活者の抱える「困窮」は、「家が無いこと」と「仕事が無いこと(仕事が出来ない人には生活保護を申請)」だと考えていた私達は、路上で出会った人々にアパートを提供し、就労支援や生活保護申請の手伝いを始めた。
最初に居宅設置をしたのは70歳近い男性だった。無事入居、生活保護の申請も出来た。ところが入居数か月後、大家から「異臭がする」との連絡が入った。訪ねるとすでに電気は止まっており、家はゴミ屋敷状態。ボランティアが総出で片づけたのを思い出す。なぜ、こんなことになったのか。私達は二つの原因を考えた。一つは「本人の要因」。何等かの障害があったのに気づかなかったのだと思う。だが、それだけではない。もう一つは「社会的な要因」である。彼は、確かにアパートに入居し、自立したが、その後も孤立状態は続いていたのだ。人はいつ掃除をするのか。あるいは、なぜ掃除をするのか。衛生上の問題か。いや、それだけではない。恥ずかしながら私など、誰か訪ねて来ないと真剣に掃除をしない。他者の存在が行動の動機となるのだ。誰も訪ねて来ない中、彼には掃除をする動機は醸成されなかった。そもそも長く野宿を生きた彼には、ゴミ屋敷の方が慣れていたのかも知れない。このような現実に変化を来らせるもの。それが「他者」の存在だったのだ。
つづく