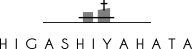2025/03/16
3/16巻頭言「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」その②
「時」の問題を理解しつつも支援現場、特に国が定めた制度の枠で動いていると「自立支援計画」に支援者も当事者も縛られる。国は、「就労自立」や「増収率」などを「成果指標」に定め判断する。「安易な成果主義」であることは知りつつ、いや、反発しつつも、このわかりやすい「成果」にのみ込まれる。
かくいう抱樸も「路上からの自立者3,700人以上」、「自立率9割以上」、「自立生活継続率9割以上」「高校進学率100%」などと報告してきた。2009年のNHK総合「プロフェッショナル仕事の流儀」では、「奇跡の数値」と紹介されたこともある。
当初は「好きでホームレスをしている人を支援しても無駄」、「本人たちに自立する意欲はない」など、ホームレス向けられた「自立支援」を否定する意見は少なくなった。しかし、北九州では全国屈指の「成果」が出た。「無理だと思われてきたホームレス自立支援が成果を出している」ということで世間からの注目が集まった。私たちは、そのことを誇りに感じたし自信にもつながっていった。
当初私たちがテーマしていたのは「人いつか変わる」だった。「変わらない」と思われていたホームレス状態の方々が出会いの中で次々に変わっていく。私たちは、希望を見ていた。2009年に放映された「プロフェッショナル仕事の流儀」でもこのことばが紹介されていた。しかし、その時点で抱樸が掲げていたテーマがもう一つある。それは「変わらなくても人は生きる」と言う事だった。
「自立支援計画」を立てて支援を実施しても計画通りにいかないこともある。国の制度では「支援開始」から始まり、定められた期間が来れば「支援終結」となる。結果が出ても、出なくても「その日」は来る。そうなると「なぜ、結果が出なかったのか」、「支援員の力量不足が原因か」、「本人の努力が足りないからか」。現場での自問自答に明確な答えはない。そんな中、「これまでの日々は無駄だったのか」とむなしささえ感じる支援員も少なくない。しかし、その要因はそんな事ではない。「時」ではなかっただけだ。「まーだだよ」と声にならない声を聞くことが出来るかが問われている。
だから抱樸は伴走型支援を生み出した。従来の「支援」は「問題解決」を目的としてきたが、実際は「何が解決か解らない」ということがしばしばおこる。例えば失業中の方への支援は「就労支援」ということになるが、なんとか就職できても「それがその方にとって幸せなのか」は別問題である。それで「解決」を出口とする「解決型支援と並行して「つながることを目的とする伴走型支援」が生まれた。 つづく