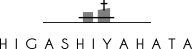2025/03/23
3/23巻頭言 「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」 その2.5(前回書き換え)
だが「自立支援計画」を立てることはできても「その人の時」を定めることは出来ない。この事実を無視して支援を進め。当然「計画通りいかない」というを起こる。そんな時「相談員としての力量不足が原因」だと考え支援員を責めたり、「本人の努力が足りない」と相談者を責めたりする。それらも原因かも知れないが、多くの場合「その時ではない」ということに起因していると思う。「人がもう一度立ち上がる時」、「再び生きようと思える時」。その「時」がいつ来るかは誰も知らない。だから「その時」まで待つしかない。
しばしば制度においては「支援目標」として「就労自立自立率」や「増収率」などが定められる。「結果」や「成果」で判断されることが多いので、ついついそういう「数値」にのみ込まれてしまう。かくいう抱樸も「路上からの自立者3700人以上」、「自立率9割以上」、「自立生活継続率9割以上」「高校進学率100%」などと報告してきた。2009年春に放映されたNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」では抱樸の自立率の高さを「奇跡の数値」と紹介された。
確かにそれは「当時の常識」からすると「奇跡的」だった。活動がはじまった30年前、「ホームレスを支援しても無駄」「好きでホームレスをしている人たちだから自立などしない」「そもそも彼らに自立する意欲はない」などと多くの人は考えていたからだ。
しかし、活動が進むにつれて全国屈指の「成果」が出た。そして世間から注目を集めることになった。私たち自身も、そのことを誇りに感じたし、自信にもつながった。そして、その経験は言葉となった。「人は変わる」。人は誰かと出会うことによって変わる。変わることができる。だからあきらめない。それが素直な気持ちだったし、私たちはその事実を「希望」だと思った。先のNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」でも「人はいつか変わる」という言葉が紹介された。
しかし、このことばを語り始めた頃、同時に私たちは悩み始めていた。「変わること」、あるいは「自立者数」や「自立率」を声高に「成果」として示す一方で、それでも「変わらない」人の現実があったからだ。すべての人が計画通りに変わっていくということはあり得ない。上手くいかない人もいるし、「時」が来ていないということもある。さらに、まずいことに「変わる」という「成果」に心を奪われると「それでも変わらない人」に対して「イライラする」ようになったのだ。「自立など絶対に無理」と言っていた世間に対して「支援をすればホームレスからの自立は可能」ということを示す意義は大いにあった。それにより国や行政による「ホームレス自立支援策」を進めることは重要だった。しかし、「変わる」ことを「成果」とし「支援の目的」がその成果に呪縛されていくことに私たちは不安を感じていた。「人は変わる」。そう言いつつ支援を続けることは「支援者側のエゴ」に過ぎないのではないか。そんな自問が湧いてきたのだ。
つづく