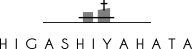2025/03/30
3/30巻頭言「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」 その③
人間は単純ではない。当然である。「自立支援計画」を立て、それに基づき支援を実施しても計画通りに進まない。国が定めた制度では「支援開始」から始まり、期間が来れば「支援終結」となる。その時(時間)までに結果を出さなくてはならない。しかし、そうならない。「なぜ、結果が出なかったのか」。そんなモヤモヤが支援員を悩ます。「自分の力量不足が原因か」、それとも「本人の努力不足」か。答えのない問いの中で「これまでの支援は無駄だったのか」と考えてしまう。確かにそういうこともあるかも知れない。
しかし、それ以上に注意すべきは「時ではなかった」ということ。支援者側がどれほど力んでみても「まーだだよ」と声にならない声が聞こえる。それを聴く耳が必要なのだ。さらに、どれだけ待ったとしてもこちらが考える「結論」、つまり「自立」には至らないこともある。支援者がアセスメントの中で定めた「主訴(本人の訴え・課題)」が本当に本人の訴えだったのか。人の生き方、幸福感はそう明確ではない。特に本人が孤立している場合は、「自己認知」が上手くできないこともある。人は他者を通して自分を知るからだ。
さらに考えなければならないことは「何かもっと大きな危機から逃れるために野宿生活を選ばざるを得なかった」という人がいること。借金、家族関係、人間関係などから「生き延びるために野宿を選んだ人」さえいる。困難な事情を抱えつつも「生き延びた」人なのだ。となれば「野宿からの自立」を目指す前に、「良く生きて来られましたね」と言うことが重要となる。
それが人の現実だとすると「人は変わる」と迫ってみても、時に「それはそっちの都合だろう」と言われてしまう。だから、ともかく伴走し、つながり、付き合い続けるしかない。
そんな葛藤の中で私たちは、もう一つのことばを考えていた。「変わらなくても人は生きる」だ。当然といえば当然なのだが「自立中心の成果主義」にのみ込まれるとこれが「当然」でなくなる。「人は変わる」「変わらなくても人は生きる」。この二つの言葉に挟まれて私たちは活動をしてきた。
実は、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」のスタッフにもこの「二つのテーマ」を伝えていたが二つ目は採用されなかった。「ホームレス支援を初めて知る視聴者に矛盾する二つのテーマを伝えるのは難しい」とのことだった。確かに。しかし、それを言わないと「美しい成功ストーリー」に終わってしまう。
抱樸の現場から生まれた「伴走型支援」は、「問題解決」を目的としてきた従来の支援、つまり「解決型支援」を大切にしつつも、それだけではない現場の、いや人の現実を踏まえたものだ。解決型支援は「変わる(あるいは変える)」ことを目的とする。「宿なしから居宅設置へ」、「失業状態から就業状態へ」、「多重債務から会計の自己管理へ」。その人が望む状態への変化を支援するのが「解決型支援」だ。
つづく