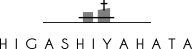2025/04/06
4/6巻頭言「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」 その④
一方、伴走型支援の目的は「変わる」ことではなく「つながること」、あるいは「付き合うこと」とした。あえて「変わる」という観点でいうならば「孤立状態から誰かと共にいる状態へ」という言い方もできる。ただ「孤立解消」と言うと「分かり合える信頼関係の構築」というイメージかも知れないがそう単純でもない。「放っておいてくれ」「今度でいい」「せからしい(鬱陶しいという方言)」「帰れ」と言われ続けても訪ね続ける。一見、「単なるおせっかい」でしかないがそれを続ける。「一方通行」のように見えるが、それ自体が「支援」なのだ。
さらに「解決型支援」において何をもって「解決」とするかは難しい。「主訴」というが、それは本当に本人の訴え(思い)なのか。例えば長年引きこもり状態にあった人が支援を受けて就職したとする。しばしば「困難事例」と言われる「長期引きこもり」が解決し就職できたのだから、これは「成功事例」として評価される。しかし、長年引きこもっていた本人からすると就職は「新たな苦難の始まり」かも知れない。
そもそも引きこもりの要因と言われているのは「小学校・中学校・高校時代の不登校」、「職場になじめなかった」、「就職活動がうまくいかなかった」、「人間関係がうまくいかなかった」とされている(内閣府調べ)。これらは自殺の要因にも重なる。何十年前のあの日、自死してもおかしくなかったその人が生き延びるために引きこもったとしたら、簡単に「引きこもり問題」とも言えない。「解決」も大切だがまずは「よく生きてこられましたね。大変でしたね」から始めることが大事だ。そして何よりもそう言いつつ「時を持つ」ことも大切だ。
ところで先日のNHK総合「新プロジェクトX」で秋田の藤里町の取り組みが紹介されていた。番組に登場された菊池まゆみさん(藤里町社会福祉協議会会長)は、生活困窮者自立支援に関する審議会部会でご一緒させてもらい、以降時々お会いする方である。菊池さんは、現在の福祉が強い人が弱い人を助け、弱い人をいたわるとい構図に終始していることを課題と感じ、その人が本来持っている力を引き出すことが大事(ストレングスモデル)と考え、支援が必要な人も支援されっぱなしではなく支援する側にもなれる地域を創る。それが地域づくりにつながると考え、「福祉のまちづくり」から「福祉でまちづくり」を実践してこられた。だから、菊池さんの取り組みはすばらしいと思う。
つづく