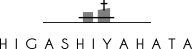2025/04/13
4/13巻頭言「人はいつか変わる。変わらなくても人は生きる」 最終回
ただ番組のタイトルには違和感を持った。「人生は何度でもやり直せる『ひきこもりゼロを実現した町』」。結果として「引きこもりゼロ」を達成したことは事実だとしても、それが果たしてすばらしいことなのだろうか、そう思った。「引きこもりゼロ」は、「結果」であって「目的」ではない。人には「時」がある。引きこもる時があり、部屋を出る時がある。何よりも「生きる」ために引きこもることもある。「引きこもりゼロ」を「良いこと」、「すばらしい成果」だと讃えられてしまうと現在ひきこもり状態にある人はどう思うだろうか。それが「成功事例」ならば今後藤里町では引きこもることができないことになる。それは誤ったメッセージだと言わざるを得ない。確かに社会のひずみなどの結果、ひきこもらざるを得なかった人にとっては、そのような「ひずみ」を取り除くことは重要だと思う。しかし、それでも「ひきこもりゼロ」を「成功事例」とされてしまうと現状引きこもりを続けている人、続けざるを得ない人、また、そのような状況を抱える親や家族はどう思うだろうか。正直、時には「生きるためにひきこもることが出来る社会」があって良いと思う。
菊池さんは、あるインタビューにこのように答えておられる。「特殊なことでもなければ、新しい理論・実践でもないと思います。繰り返しになりますが、ご本人がやりたいと思うことを応援するということに尽きます。福祉職が陥りがちなことですが、相談を受けてそれに応じていると、何か自分が救ってやったような錯覚を覚えることがよくあります。(中略)ご本人の自己実現のため、今の生活をより良くしていくため、ありとあらゆる社会資源を提示する、必要な社会資源がなければ頑張って新しい資源をつくる。それが基本ではないでしょうか。」(新公民連携街づくり―PPPでまちづくり『麓幸子の「地方を変える女性に会いに行く!」』2016年9月12日)。その通りだと思う。だからこそ、積極的であれ消極的であれ「ひきこもる」ことをその時の自己実現として選び取ることは許されるべきだと思う。菊池さん自身「ひきこもりゼロを実現した町」というタイトルをどう感じられたのか、いつか聞いてみたい。
抱樸は、「人は変わる」と「変わらなくても人は生きる」と言う矛盾したテーマを引きずって活動してきた。抱樸のみならず人と向き合い共に生きるためにもがく人々、そして自分は何をしたいのかを捜しもがく人々は、この逆説的な課題の間に惑いつつ日々を過ごしておられると思う。それは人が生きるということの深みそのものを示している。だから「ゼロ」などと簡単に言って欲しくないのだ。 おわり