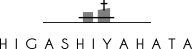2025/04/27
4/27巻頭言「日本福祉大学卒業式祝辞」 後編
(先日、日本福祉大学の卒業式に呼ばれ祝辞を述べた。現在、私はこの大学の客員教授ということになっている)
弱さを「つながり」の根拠にする。「ひとりでは生きていけない」という「共通した認識」が必然的に他者を求める。これが人間です。他者を「えじき」にし「自分だけ良ければいい」と言っていると、いずれネアンデルタール人の二の前になります。
さて、皆さんは、今日「学校」という教育機関を卒業されるわけです。学校教育の根底にあるものは「狭い意味での自立」だと私は思ってきました。「自立した人間の育成」、「自分の力で生きていくことができる人間の育成」、それらが学校教育の目的だと、私自身の学校時代を振り返ると思うのです。学校教育において社会保障制度活用の仕方を教えないのはこのためです。例えば生活保護や失業保険の申請の仕方を教えない。それは「社会保障などに頼らなくても生きていける人を育てる」ことが教育の目的になっているからです。
「強者教育」と言っても良いかもしれません。個々の教員の思いは当然それだけではありませんが、教育システムとしての学校教育はそうだったと思います。
2020年の労働力調査によりますと、現在35歳以下の26%が年収186万円以下のアンダークラスだそうです。にも拘わらず多くの若者は社会保障を活用しません。
制度に対するスティグマ(差別意識)があるのも事実でが、理由はそれだけではありません。教えられていないからです。知らないと制度は使えません。2023三年度、休職された公立学校の先生は7,000人を超えました。それぞれつらい思いをされていると思います。「教師なのに学校に行けない。教師失格」。そんな思いの方もおられると思います。「自立した人間を目指す」は教師にとってもプレッシャーです。
私自身も弱い人間です。すべてが嫌になってどこかに行きたいと思う日もあります。そんな日が人生には確かにあります。しかし、見方を変えると休職中の先生は「生きた教育」をされているのかも知れません。「教師といえども倒れる時がある。たとえ倒れても病気休職や傷病手当など使える制度がある」。制度を活用し、時が来れば復職したらよいのです。
大人になった生徒がもし倒れたとしても、あの日の先生のことを思い出すでしょう。「先生もそうだった。一旦休んでやり直せばいい」。休職中の先生方は、人間の本質や社会の存在意義、さらに本当の「自立とは何か」を教えておられるのかも知れません。
今日、みなさんは「福祉」という名前のついた大学を卒業されます。「福祉」は、「人間が脆弱であるという事実」を前提として、「人は助け合うことで幸せになれる」ということを意味します。これが「他者性のある自立」ということです。長い人生において時に倒れることもあります。それは、あなたが人だからです。それが人間だからです。心配しないでください。その日、あなたは「人とは何か」、 「人間とは何か」、そして「社会とは」、あの時学んだ「福祉とは何か」を知るのです。
私から申し上げたいことは以上です。本日はご卒業おめでとうございました。