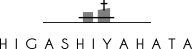2020/03/08
3/8巻頭言「希望の牧場が問うもの―東日本大震災から九年・基底とは」
福島県浪江町の山裾にその牧場はある。「希望の牧場」と呼ばれている。そこには300頭以上の牛が今日も「生き続けている」。私がその場所を始めて訪れたのは、震災から7年が経過した2018年春のことだった。
2011年3月11日の東日本大震災の翌日、福島第一原発1号機が爆発した。原発から20キロ圏内が警戒区域に指定され、町から人の姿が消えた。「希望の牧場」の元は、エム牧場浪江農場で、原発から14kmにあった。警戒区域には、牧場が多く存在し、多くの牛や豚が飼育されていたが、半数以上は餓死したと言われている。所有農家の承諾を得たうえで殺処分された牛も多いという。農場長だった吉沢正巳さんは、この殺処分を拒否。町中が避難した後も牧場に残り牛の面倒を見続けた。吉沢さんは「ここの牛はもう売れないから経済価値はない。家畜でもペットでもない。動物園にもならないよね。なんのために飼うのかと、俺自身考え続けた。でも、俺は牛飼いとして殺すわけにはいかないんだ」と言う。現在では「希望の牧場・ふくしま」は、一般社団法人となり、全国からのカンパで今日も牛たちを生かし続けている。
東日本大震災では、死者・行方不明者を合わせて24,585人(2019年12月時点)が犠牲となった。放射能の惨禍を考えると改めて大変な事態だと改めて思わされる。
あの日、私達はすべてのモノがそぎ落とされたように「いのち」に集中していた。なにはともあれ「生きている」ことの意義と絶対的な価値を理屈抜きで理解した。それこそが死んでいった人々に対する「責務」のように感じていた。
だが、あれから9年、私達は「いのちよりも大切なものがあるかのような幻想」に再び生き始めている。このように言うと「そんなきれいごとを言ってもね」とすぐさま反応が返って来るが、それでも「それは幻想だ」と言いたい。なぜなら9年前、確かに私達は「いのち」ということの絶対的で普遍的な価値の前に素直にうなづいていたからだ。私達は「生きている」ことの意味を噛みしめていたからだ。
「経済価値がない牛」を生かし続ける吉沢さんや希望の牧場の姿は「生きる意味のあるいのち」と「生きる意味のないいのち」を分断する今日の日本社会を静かに問うているように思う。もうすぐ、相模原事件の判決を迎えるが、あの事件を2011年3月11日から振り返ることが必要だと思う。あるいは1945年8月15日から見つめ直すのだ。
「いのちの底が抜けた日」、私達は「それこそ」が「基底」であったことを知った。それが無ければ何もない。経済もクソもない。オリンピックも復興も、すべてはこの「基底」が無ければ成立しない。今年も3月11日を迎える。思い出すとつらくなる人々が少なくないことを知りつつ、それでもあえて「私達はあのいのちの底が抜けた日を心に刻まねならない」と言おう。
イエスは言う。「人が全世界をもうけても、自分の命を損したら、なんの得になろうか」。(マルコ福音書8章)その日は、いのちそのものを噛みしめたいと思う。