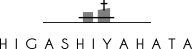2017/06/23
いのちが分断される時代―障がい者殺傷事件から見えた風景
二〇一六年七月二六日。相模原市の障がい者施設で起こった殺傷事件に私は大きな衝撃を受けた。現在裁判中であり、被告に関して深くも知らず、あるいは当該の障がい者施設の実態にも詳しくないので、今回の事件そのものに関して語ることはできない。しかし、この事件から見えた現代社会の風景について少し述べたいと思う。
一九人死亡という結果の重大さもさることながら、彼が「確信犯」であったことに驚愕する。「確信犯」は一般に「悪いことだと承知で罪を犯す人のこと」と理解されるが本意は違う。「確信犯」とは、「信念に基づき悪いことでないと確信して罪を犯すこと」を意味する。確信犯は「悪いことを承知で罪を犯す人」ではなく、「良いことをしていると確信して罪を犯す人」なのだ。彼は確信犯であった。
では、彼の確信とは何であったのか。事件前、衆議院議長宛ての手紙に「障がい者は家族を不幸にしている」「日本と世界の経済のためにやる」と彼は自分の犯行の意義を説いている。「不幸をもたらす」「生きる意味のない」存在と障がい者を意味づけ、殺害することこそ「良いこと」であり、自らの使命だと彼は「確信」していたと思う。
一つの事件を思いだす。三十年以上前の一九八三年、横浜で中学生らがホームレスの男性を殺害した。「横浜『浮浪者』殺人事件」である。当時、ホームレスという言葉もなかった。一八歳だった私は同世代の犯行に驚いたが、それ以上に衝撃を受けたのは彼らが逮捕後語った言葉だった。「横浜の地下街が汚いのは浮浪者がいるせいだ。俺たちは始末し町の美化運動に協力してやったんだ。清掃してやったんだ。乞食なんて生きてたって汚いだけでしょうがないでしょ。」中学生らも「確信犯」であった。彼らは、ホームレス襲撃を「町の美化運動」と呼び、「社会貢献」でもしているかのようにホームレスを殺した。
「ホームレスは町のゴミ」と言う差別意識や「始末」としての排除は、その後各地に広がった。住民らが「地域の安心と安全を守る」ためにホームレスを排除し、支援施設の建築が住民反対で止まった。住民は、それを「町づくりだ」「良いことだ」と「確信」していた。そして「排除されるいのち」と「守られるいのち」の分断が起こった。あれから三十年。相模原の事件は横浜の事件の帰結のように思えた。
声を大にして言いたい。「意味のあるいのち」と「意味のないいのち」などない。いのちに意味がある。この普遍的価値についてゆるぎなく言い切ることが現代においては何よりも大切だ。
一方で「意味のあるいのち」かどうか、というプレッシャーは、同時代を生きるすべての人々を脅かす。横浜の中学生は加害者である一方で、彼らもまた「意味のあるいのちか」を問われていた存在だった。中学生にとって「意味のあるいのち」とは、「良い成績を取ること」だとしたら、それが叶わない子どもは、自分の存在の意味をどうやって証明するのか。中学生らは「町のゴミを始末する」ことで、自分の存在意義を証明しようとしたのではないか。
相模原事件の青年も同様に「意味のないいのち」というプレッシャーの中に置かれていたのかも知れない。大学卒業後、就職も上手くいかず、その後措置入院。存在意義を証明するために犯行に臨んだとすればどうだろうか。当然、どんな理由があったとしてもあの凶行は赦されない。しかし、生産性や経済効率性が偏重される時代の中で、自分が「意味のあるいのち」であることを証明しようと多くの人が追い詰められているのも事実である。他ならぬ私自身もそうだ。
ナチスに抵抗したニーメラー牧師は、戦後このような言葉を残している。「ナチスが共産主義者を弾圧した時、私は不安に駆られたが、自分は共産主義者でなかったので何の行動も起こさなかった。その次にナチスは社会主義者を弾圧した。私はさらに不安を感じたが自分は社会主義者ではないので何の抗議もしなかった。それからナチスは学生、新聞人、ユダヤ人と順次弾圧の輪を広げていき、そのたびに私の不安は増大したがそれでも私は行動に出なかった。ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた。そして私は牧師だった。だから行動に立ち上がったが、その時はすべてがあまりにも遅かった」。
一九八三年横浜でホームレスを襲撃された。私はホームレスではなかったので何もしなかった。その後、各地でホームレスの排除が起こり、施設建設の反対運動が激化した、だが私には関係ないと思っていた。二〇一六年相模原で重い障がいのある人々が殺された。私は障がい者ではなかったし、家族にも障がい者はいなかったので何の行動にも出なかった。しかし、これらの事件の根底に「意味のないいのちは排除する」という考えがあるとしたら、この分断はすでに私を含め浸透している。いずれの日か「遅かった」と悔やむことがないように「いのちに意味がある」と言い続けたい。
私は問われている。あの犯人の青年になんというかを。「あれだけの罪を犯したのだ。君には生きる資格などない。お前は死刑だ」と言うべきか。「当然だ」と思う人は少なくない。被害者の事、その家族の事を考えるとなおさらである。しかし「生きる意味はないから死刑だ」と私たちが言うならば、それはまさに彼の言ったことを、今度は彼に対して私が言うことになる。答えは簡単ではない。容易ならざる問いの中で呻吟するしかない。それがいのちと向かい合うことなのだと思う。
いのちの分断が進んでいる。権力者は、「ファースト」を叫び民衆や国を分断する。当初は、「自分はファーストの範疇にいる」と安心できたとしても、所詮分断された世界の片側にいるに過ぎない。その分断がある時逆転する、途端に私はセカンド(二の次)となる。分断自体を否定する生き方を求めるしかない。